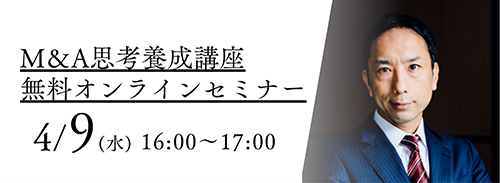<
山口恵里の“現場に行く!”2025年4月号
「第65回:今、中小企業に必要な『M&A思考』
〜実践的M&A知識と自分ごと化の情報リテラシー〜」
皆さん、こんにちは!スモールサン事務局の山口恵里です。
今月の「山口恵里の“現場に行く!”」では、ちょっと趣向を変えて、スモールサンM&Aプロデューサーであり株式会社オプティアスの代表取締役、萩原直哉さんにお話をお聞きしました!

事業承継問題を背景に、中小企業にとっても急激に身近な存在になったM &A。以前は大企業のものというイメージが強かったですが、今では中小企業にとっても重要な戦術として必須なものとなりつつあります。
その一方で悪質M&Aと言われる詐欺まがいの事件がメディアを賑わせているのもまた事実です。
そこで長年中小企業のM&Aを手掛けてきた専門家である萩原さんに、最近の中小企業のM&A事情とともに、スモールサンでも大切な学びとして講座を開いている「M &A思考」についてもお聞きしました!
4月9日はM &A思考オンラインセミナー、5月からはM&A思考養成講座第4期も開催予定です。
ご興味のある方はぜひ本記事もご覧くださいませ!
【萩原 直哉氏プロフィール】
スモールサンM&Aプロデューサー
1968年茨城県生まれ
株式会社オプティアス代表取締役
中小・零細企業を専門としたM&Aアドバイザー。
大手信用調査会社の調査員として延べ1,500社を超える企業の経営者と面談した経験を活かした「中小企業経営者・オーナーの目線に立ったM&A」がモットー。
従来、スポットの当たりづらかった小規模な案件でも積極的に取り扱う姿勢を貫き、実践的M&Aの手法を活用して中小企業の様々な経営課題の解決に取り組んでいる。
中小企業にも広がるM&A
山口:では、早速ですが最近のM&A事情についてお聞きしたいと思います。10年くらい前は、「M&Aって中小企業でもできるんだよ」という啓蒙段階のイメージだったんですが、ここ数年で一気に変わってきている印象があります。
萩原:M&Aの会社が今10社弱ぐらい上場していたり、テレビCMをバンバンやったりしているのもあって、一般の人にも「M&Aって身近な話だな」と感じてもらえるようになってきてますね。もう一つは…これは褒められたことじゃないんだけど、M&Aの会社がバンバンDMや電話をしていて、中小企業庁もそれで規制入れたりしてます。そういう激しい営業活動で認知された部分もあって、事業承継のM&Aというのがすごく掘り起こされたと思います。
山口:やっぱり広がる最初のきっかけは、中小企業の事業承継問題というのが後押しした感じなんですかね?
萩原:そうですね。私が関わっている案件でも、やっぱり社長の高齢化、事業承継の話が多いです。私のM&A思考の講座でも、「後継者がいないから誰か買ってくれないかな」と思って参加してくれた60歳オーバーの経営者がいて、でもその人は途中で「いや、私買えるんじゃない?」と気づいて買う側に回りました(笑)
山口:それも凄いですね(笑)
萩原:それで、むしろ「私、もっと頑張ろう」みたいになるケースもあります。もちろん一般的には高齢の経営者が会社をより若い人にというのが事業承継だけど、そうじゃないケースも出てきてる。昔と比べて経営者の現役年齢が上がってるから、70や80まで元気に会社やっている人も多いですからね。その一方で「60歳過ぎぐらいを目処に会社を譲ろう」というM&Aも増えてる印象ですね。
近年特に増える再生型M&A。比べて増えない“専門家”の存在
萩原:それと最近特に増えているのが「再生型M&A」ですね。ゼロゼロ融資、いわゆるコロナ融資の返済ができなくて倒産するケース去年くらいから増えているので、それに伴って債務過多で再生しなきゃいけないというM&Aが今、結構増えてます。
山口:再生型というのは具体的にどういうものなんですか?
萩原:再生型M&Aというのは、ざっくり言うと経営に行き詰まった会社がM&Aを活用して事業再生を図る手法です。方法は色々ありますが、例えば金融機関と交渉して3億円の借金を1億円に減らしてあげて、事業だけちゃんと切り出してスポンサー企業に事業譲渡という形で渡す。民事再生で倒産した後に裁判所と話をつけて、倒産した会社の事業だけ引き受けるとかね。会社は畳んでも事業が継続されることで従業員や取引先が救済されるほか、M&Aの売却対価が入ることで弁済率が上がるので債権者としてもメリットが大きいです。
山口:なるほど。倒産が増えている今、とても重要な選択肢になりますね。
萩原:そうですね。ただこれ、対応できる専門家が少ないんです。例えば普通に売上も利益も出てるような会社なら、金額がいくらになるかはさて置き、買い手はつきやすいですよね。でも赤字で債務超過の会社ですってなったら買いたいですか?
山口:いや、それはとても…。
萩原:そう、「とても…」ってなっちゃいますよね。でも、そういう会社でもさっき言ったように債務をカットして事業の中身を切り出して…と手を入れることで、ちゃんと引き受け手が出てくるんですよ!ところが弁護士や専門家でも知識がなかったり、あっても「面倒くさいからやらない」ってケースも多いんです。だから事業承継型でも、順調な会社なら色々なM&A仲介会社が出てきて相手を見つけてM&Aを進めてくれるけど、事業承継したくても赤字で借金いっぱいあって…という会社は、再生型で救ってもらえなければ清算してなくなっちゃう。これからもっと問題になるんじゃないかな。
山口:実際に経営が苦しい会社でも、ちゃんとスポンサー企業がついて事業が再生しているケースもあるんですよね。
萩原:勿論です。むしろ、今の経営者でうまくいっていない会社ほど、借金ゼロで引き継げるならやりたいって人もいます。利益が出てる会社だと何千万円、何億円と払わなきゃいけないけど、うまくいってない会社なら従業員を引き継いで安く買えたりもする。そういう再生が得意な会社って意外と存在するんですよ。例えば飲食店やお惣菜の会社とか、単独ではヒーヒー言ってたのを、他の業態を複数持ってる会社がグループに取り込むことで、仕入れをグループ内にしたり、販路を共通化したり、ちゃんとシナジーがあって再生してる。経営者が変わったり、違うグループに入るだけでうまく回るケースって、実はすごく多いんですよ。ただ、それを専門家がちゃんと分かっていないと、再生型M&Aはうまくいかない。
山口:今何がネックになっていて、何をどうすれば伸びるといった視点がないと難しいですよね。
萩原:それがまさに大事ですね。そういった再生のノウハウを持った「再生のプロ」という存在はこれから更に必要になっていくと思いますね。
急増する詐欺まがいの悪質M&A被害
萩原:ところが、この再生型M&Aの増加と専門家不足を背景に、今詐欺まがいのM&Aによる被害が急増しているんです。
山口:どういった手口による被害なんですか?
萩原:例えば債務超過で赤字だしもうどうしたら良いのか分からないと悩んでる社長さんがいるとします。今のまま自分がこの会社をやっていてもどうにもならないし、赤字ばかりで借金も返せない。でも、借金は個人保証しているから、もしもこけたら自分の財産を売って返済しなきゃいけない。そこに“再生のプロ”を装って近付くわけです。「株価はタダ同然だけど、事業は全部引き継いで立て直すし、借金の個人保証も引き受けますよ」と。
山口:そんなうまい話そうそうないですよね…。
萩原:その通りで、普通はそのまま引き受けるというのは無理です。我々であれば、スポンサーになってくれる企業を探して、ここなら事業を再生できるはずですと。でも債務は減らさないといけないから、まず銀行と交渉しましょうよとなります。中小企業の事業再生や収益力改善に関するアドバイスをおこなう中小企業活性化協議会という公的機関があるんですが、そういうところと弁護士や再生のコンサルタントが組んで計画をつくって、「こうすれば雇用も守れるし、スポンサー企業がお金を入れてくれるから、回収できるお金も増える。そのまま置いておくとゼロだけど、このスキームに乗ればちょっと返ってくるから、やりませんか?」と相談して手間をかけながら再生に向かっていくわけです。当然社長も多少の痛みは負いながら頑張らなきゃいけない。ところが悪質な業者の場合、「いやいやいや、そんなことしなくても大丈夫です!株はタダだけど全部そのまま引き受けますから!」と言われるから、そっちの方がよく聞こえちゃうんですよね。
山口:まさに甘言ですね。それに釣られてしまうとどうなるんですか?
萩原:実際に契約書を作って譲った瞬間から、じゃんじゃか現金を抜き始めます。ナントカさんというのが会社に入ってきて、大して儲かってもいないのに役員報酬だと言って毎月100万円持っていかれる。酷いケースだと生命保険まで解約して持っていかれることもあります。個人保証の付け替えも当然しません。社長がいつ銀行に行くのか聞いても、忙しい忙しいと言って行かないわけですよ。そうこうしている内にさっさといなくなっちゃうんです。
山口:それってもう完全に詐欺のように思えるんですが、相手が捕まったりしないんですか?
萩原:そこがまた難しいんですよね。今そういう事件で何社か実名で報道されている会社はあるんですが、1社は逃げてしまって行方知れず。でも一応警察が追っているようです。あと1社は潰れて、他の2社はまだ営業しているんです。
山口:え!営業してるんですか!?
萩原:そうなんですよ。例えば、AさんがB社の被害にあって、「これは詐欺だ!契約通り履行してくれない!」と訴えたとする。でもB社の人は、「いや違うんですよ。今一生懸命頑張ってるんです。あと1か月したら入金があるから、ちょっと待ってください」という。それで待ってみるけど当然入金はない。その後も「すみません、今ちょっと遅れているんです」「もうちょっと待ってください」この繰り返しです。強制執行とかで会社の財産を押さえるまで証拠がつかめれば良いけど、詐欺として意図的にやったのか、頑張ったけど駄目だったのかって第三者が判断するのって難しいでしょう。で、ある日突然、潰れることもある。
山口:なるほど…。だから多くのメディアでも「吸血型M&A」や「悪質M&A」等のあくまでも“詐欺的”な表記なんですね。
仲介会社ですら騙される
〜「専門家に任せればOK」はもう危ない〜
萩原:もう一つ大事な問題なのが、そういう悪質な会社に中小企業を紹介したのはM &Aの仲介会社なんですよ。
山口:それって良くない会社だと分かってて紹介してるんですか?
萩原:多くのケースでは、仲介会社のアドバイザーすら見抜けないまま紹介しているように思います。実際私のところにもあるM&A仲介会社の若いアドバイザーが、「こんな良い会社があるので、萩原さんの案件で紹介してください」と言って来たので、どんな会社か資料をもらったことがあるんですが、これが明らかに怪しい会社なんですよ。彼にもそう言ったんですが、「いや、判断が早くてすごく良い買い手なので、とにかく会ってみて下さい!」と聞かない。それで「会ってもいいけど、ボコボコに言うよ?」と言ったら諦めましたが、彼の言う「良い買い手」が今悪質M&A問題で実名報道されているルシアンホールディングスでした。
山口:M&A仲介会社って、つまり「M&Aの専門家」ですよね。その専門家でも見抜けないって怖いですね…。
萩原:事業承継問題で中小企業のM&Aが増加したことで、M&A仲介会社も急激に増えました。当然その中にはキャリアの浅いアドバイザーも多くいます。そして成功報酬型のM &A仲介会社は多いですから、キャリアの浅いアドバイザーは数字に追われて、ホイホイ買ってフィーを払ってくれる会社に騙されちゃうんじゃないかなと思いますね。ここで問題なのが、仲介会社は詐欺まがい会社からもフィーをもらってるということです。間違いを認めて返した会社もあるけど、返してなくて揉めているところもあります。
山口:うーん。M&Aという手法はしっかり確立されたものがあると思うんですが、そういうトラブルであったり悪用であったりを防ぐような法整備が追いついてないんですかね?
萩原:追いついてないですね。中小企業庁がM&A支援機関登録という、M&Aのアドバイザーや仲介会社を登録する仕組みを4年前に始めました。それは報告義務もあるんだけど、それでも結局登録だけだから、やったことない人が登録してたりもするんです。恐らく中小企業庁としては、M&A事業者をとにかく集めて篩にかけようとしてるんじゃないかと思うんですけどね。それで今回の詐欺まがい事件に関わったM&A仲介会社15社に対して是正勧告が出ました。その中で従わなかったと思われる1社は実名を公表されて支援機関の登録からも除名されました。
山口:え、それだけですか?
萩原:そう思いますよね!実際除名されても絶賛営業中ですからね。罰則がないんだもん。
今、中小企業に必要な「M&A思考」
〜戦術としてのM&A知識と、戦略構築のためのビジネス・リテラシー〜
萩原:こういうのって、やっぱり経営者自身がある程度の知識や情報を持っておくことが大事なんです。相手の言っていることが本当に妥当かどうか、自分にある程度の知識があれば明らかにおかしい話には気づけるはずなんです。
山口:「専門家に任せておけば大丈夫」って、結構多くの人が考えがちだと思います。でも、自分に知識や情報がなければ、その人が本当に任せて大丈夫な専門家なのかどうかも見極められないんですよね。
萩原: それでなくてもM&Aって難しそうだから、「専門家です」とこられると言いなりになってしまいがちになる。そうすると、やたら高い報酬払わされたり、「ちょっとどうなの?」という会社を買わされたり…。そう、昔はM&Aというと買い手側がリスキーだったんですよ。譲渡してもらっていきなり資金ショートしたり、工場付きの会社を買ったら土壌汚染でどうしようもない土地だったとかね。ところが、今は売り手側が詐欺まがいの事件に巻き込まれるという新しいパターンが出てきたわけです。これを避けるにはまずM&A自体の知識が必要だし、同時に世の中の変化とか情報を自分ごと化して活用できる思考が必要です。
山口:知識だけでなく、その知識を活かせる思考力が必要なんですね。
萩原:今私がやってる「M&A思考養成講座」の目的もそういうことです。実にいい流れのCMですね(笑)。私が経営者にこの講座を受けてほしいと言っているのは、知識がないことで中小企業の経営者側が痛い目に遭うのを何とかして回避させたいというのが大きな狙いではあります。私の知ってる会社さんで、良い案件だと銀行から持ち込まれたと言うから見せてもらったら、相当ヘロヘロな会社だったことがあって。それで「ココとココ突っ込んでみて」って行かせたら、「銀行に謝られた。危うく数千万払うところだった」って戻ってきたこともあります。
山口:銀行でそれは怖いですね…。
萩原:それにM&Aの分野も割とブームがあって、今から20年ぐらい前は調剤薬局のM&Aが流行ってたり、ちょっと前は土木工事の人気がなかったけど、少し経ったら大人気になっていたり。世の中のすう勢と共に変化するので、例えば自分の業種や業態に合わせて、今後どう変化するのか、今なら何がチャンスなのかを考えられないとM&Aをしても狙った効果が得られなかったりする。M&Aって要は戦術的な手段です。自分の会社をどの方向に向かわせるかという5年10年を見越した戦略がなければ、戦術を使う意味がないんですよ。それで、M&A思考の講座では、M &Aの実践的知識ともう一つ、世界のビジネスの潮流やビジネス環境の変化を俯瞰的に見る「ビジネス・リベラルアーツ」を両輪で学んでいます。「戦略のない戦術はカオス。戦術のない戦略はファンタジー」とよく言うでしょう。
山口:戦術の知識と戦略眼を身に付けるのが「M &A思考」なんですね。さらに言うと、定期的に講座を受けることで、何かあれば相談できる専門家とのネットワークができるというのも大きいと思います。
萩原:そういう意味では、M&A思考は4名の講師が関わっているので、複数の専門家に意見を聞けるのもメリットですね。自分で言うのもなんですが、萩原がずっと正しいとは限らないからね。情報を自分ごと化するためには、情報を鵜呑みにしないって重要だと思うんです。自分で調べてみたり、他でも聞いてみるといった癖はつけておいた方が良いと思いますね。
山口:M&A思考養成講座は5月から第4期の開催を予定しています。それに先駆けて、4月9日には無料の「M&A思考」オンラインセミナーを開催しますので、これを機に一人でも多くの中小企業経営者にM &A思考に触れてみていただけたらと思います。本日はありがとうございました!